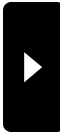2009年08月28日
選挙あれこれ(その1小選挙区選挙について)
いよいよ今度の日曜日は総選挙の投票日となりました。

なにげに使っている「総選挙」の言葉ですがこんな定義があるんですねぇ。
総選挙とは「公職選挙法上、衆議院議員の定数(480人)すべてを一度に改選する選挙をいう。」
再選挙や補欠選挙を指す「特別選挙」に対する呼び名でした。
所で今回の総選挙で衆議院議員の定数である480人が当選する事になるわけですが皆さんはどうやって480人が選ばれるか御存知ですか?
バカにするなとおっしゃらずに御存知の方ももう一度おさらいをしてみましょう。
総選挙の当選者には小選挙区の当選者と比例代表による選挙の当選者の2種類があるのは皆さんすでに御承知の通りです。
そして小選挙区の当選者が立候補している選挙区の中で最高の得票数があった候補者一人だけと言うのも良く知られた事ですよね。
ここで問題です。
立候補した選挙区の中で最多数を得票したのに当選とは認められない場合がありますがそれはどのような時でしょうか?
正解は「最多票を取ってもそれが有効投票総数の6分の1に達しなかった時」です。
公職選挙法では小選挙区の当選者について「最多得票者であってなおかつ有効投票総数の6分の1に達している事」と定めているんですねぇ。
なるほど、最多得票で有効投票総数の6分の1を超えているから当選だっ!と喜んでいる候補者の先生、喜ぶのはまだ早いですよ。
他にももう一人最多得票者がいないとは限りません、そうです、最多得票数が同じで二人以上が並んでしまった時です。
そこで次の問題です。
最多得票者が複数人同じ得票数で並んでしまった時はどうやって当選者を決めるのでしょうか?
正解は「くじ引きで決める。」です。
更に同じ選挙区に同姓の候補者が複数立候補した場合で投票用紙に複数人いる候補者の姓だけしか書かれていなくてどの候補者に入れられた票なのかわからない場合、その票の行方はどうなるのでしょうか?
正解は無効票とはならず、「候補者の得票数に応じて案分される。」です。
例えば山本さんという候補者が3人いたとして仮に山本Aさん、山本Bさん、山本Cさんとします。
そしてそれぞれの得票数がA:300票、B:200票、C:100票だったとして山本としか書かれていない票が6票あったとしたら3:2:1に割り振られる事となりAさんに3票、B、Cさんにそれぞれ2票と1票が割り当てられる事になります。
ここでは例えとして割り切れる数を例に出しましたが実際には割り切れない数字になる事もありますので得票数が必ずしも整数ではなくても良いわけです。
さて、これで小選挙区の選挙については大体おさらいが出来たかと思いますがもう一つだけ同姓同名の候補者が同じ選挙区に立候補した時の事を考えてみましょう。
これも同姓の票の場合と同じですがまずどちらの候補者に投票したのかがわかるような記載例えば政党名とか年齢とか住所を併記しての投票を促します。
通常の場合は候補者の氏名以外に書いてはいけない事が決められていてそれを書いた時は無効票となるのですがこういう場合は特例として認められているのだそうです。
これによって確実にどちらに投票したのかがわかる分を算出してどちらかわからない票を案分するのだそうです。
この同姓同名選挙ですが実際にあったと言いますから驚きですねぇ。
Wikipediaによりますと
1958年の衆院議員選挙長崎2区には、北村徳太郎(自民前、元大蔵相、71、佐世保市在住)と同姓同名の北村徳太郎(無所属新、会社役員、45、松浦市在住)が立候補。日本初の同姓同名候補による選挙戦となった。
長崎県選挙管理委員会は、按分票による開票の混乱を避けるため、有権者に対し、両者の区別がつくような文言(「前大臣の」
「佐世保の」「無所属の」「40代の」など)を投票用紙に記入するよう呼びかけた。
当初、開票作業の混乱が予想されたが、得票数は前職・北村が5万6千票強の貫禄勝ち。
新人の北村は4百票に満たない泡沫候補であった。
小選挙区について書いていたらこんなに長くなってしまいましたので比例代表については明日に譲る事にしたいと思います。
なにげに使っている「総選挙」の言葉ですがこんな定義があるんですねぇ。
総選挙とは「公職選挙法上、衆議院議員の定数(480人)すべてを一度に改選する選挙をいう。」
再選挙や補欠選挙を指す「特別選挙」に対する呼び名でした。
所で今回の総選挙で衆議院議員の定数である480人が当選する事になるわけですが皆さんはどうやって480人が選ばれるか御存知ですか?
バカにするなとおっしゃらずに御存知の方ももう一度おさらいをしてみましょう。
総選挙の当選者には小選挙区の当選者と比例代表による選挙の当選者の2種類があるのは皆さんすでに御承知の通りです。
そして小選挙区の当選者が立候補している選挙区の中で最高の得票数があった候補者一人だけと言うのも良く知られた事ですよね。
ここで問題です。
立候補した選挙区の中で最多数を得票したのに当選とは認められない場合がありますがそれはどのような時でしょうか?
正解は「最多票を取ってもそれが有効投票総数の6分の1に達しなかった時」です。
公職選挙法では小選挙区の当選者について「最多得票者であってなおかつ有効投票総数の6分の1に達している事」と定めているんですねぇ。
なるほど、最多得票で有効投票総数の6分の1を超えているから当選だっ!と喜んでいる候補者の先生、喜ぶのはまだ早いですよ。
他にももう一人最多得票者がいないとは限りません、そうです、最多得票数が同じで二人以上が並んでしまった時です。
そこで次の問題です。
最多得票者が複数人同じ得票数で並んでしまった時はどうやって当選者を決めるのでしょうか?
正解は「くじ引きで決める。」です。
更に同じ選挙区に同姓の候補者が複数立候補した場合で投票用紙に複数人いる候補者の姓だけしか書かれていなくてどの候補者に入れられた票なのかわからない場合、その票の行方はどうなるのでしょうか?
正解は無効票とはならず、「候補者の得票数に応じて案分される。」です。
例えば山本さんという候補者が3人いたとして仮に山本Aさん、山本Bさん、山本Cさんとします。
そしてそれぞれの得票数がA:300票、B:200票、C:100票だったとして山本としか書かれていない票が6票あったとしたら3:2:1に割り振られる事となりAさんに3票、B、Cさんにそれぞれ2票と1票が割り当てられる事になります。
ここでは例えとして割り切れる数を例に出しましたが実際には割り切れない数字になる事もありますので得票数が必ずしも整数ではなくても良いわけです。
さて、これで小選挙区の選挙については大体おさらいが出来たかと思いますがもう一つだけ同姓同名の候補者が同じ選挙区に立候補した時の事を考えてみましょう。
これも同姓の票の場合と同じですがまずどちらの候補者に投票したのかがわかるような記載例えば政党名とか年齢とか住所を併記しての投票を促します。
通常の場合は候補者の氏名以外に書いてはいけない事が決められていてそれを書いた時は無効票となるのですがこういう場合は特例として認められているのだそうです。
これによって確実にどちらに投票したのかがわかる分を算出してどちらかわからない票を案分するのだそうです。
この同姓同名選挙ですが実際にあったと言いますから驚きですねぇ。
Wikipediaによりますと
1958年の衆院議員選挙長崎2区には、北村徳太郎(自民前、元大蔵相、71、佐世保市在住)と同姓同名の北村徳太郎(無所属新、会社役員、45、松浦市在住)が立候補。日本初の同姓同名候補による選挙戦となった。
長崎県選挙管理委員会は、按分票による開票の混乱を避けるため、有権者に対し、両者の区別がつくような文言(「前大臣の」
「佐世保の」「無所属の」「40代の」など)を投票用紙に記入するよう呼びかけた。
当初、開票作業の混乱が予想されたが、得票数は前職・北村が5万6千票強の貫禄勝ち。
新人の北村は4百票に満たない泡沫候補であった。
小選挙区について書いていたらこんなに長くなってしまいましたので比例代表については明日に譲る事にしたいと思います。
Posted by 賢パパ at 03:28│Comments(0)
│ちょっとした知識
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。