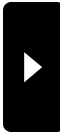2011年09月14日
ひょうちゃん
先日の夕飯にこんなものをいただく機会に恵まれまして・・・

勿論大変おいしくいただきましたよ。
で、食べながら思ったんですが・・・これの正式な呼び方って・・・シウマイ?
賢パパはもちろん崎陽軒の呼び方に倣ってシウマイと呼ばせていただいておりますが・・・
中華食堂のメニューなんかを見るとシュウマイ、あるいはシューマイなんてのも目にします。
まぁ、例によって調べてみたんですが・・・・シウマイというのは崎陽軒さんの命名らしいですねぇ。
ついでですが、こんなどうでもいいようなことを真面目に議論している方がいるんですわ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11814071
所詮は外国の食べ物で外国語の呼び方を日本人の耳で聞くわけですから正確な発音なんて再現する方が無理というものなんですよねぇ。
そんな事よりも面白い項目を見つけましたよ。
上の写真の手前に写っている物体なんですが・・・なんだかおわかりでしょうか?
これ、シウマイについている醤油入れなんですが、ちゃんと「ひょうちゃん」と言う名前がついてるんですってねぇ。
昭和30年代と言いますから賢パパが小学生の頃かも知れませんがこれが初代の「ひょうちゃん」だそうです。

昭和63年には2代目が登場して

平成17年、18年のクリスマス限定バージョンも

最新は平成20年の100周年記念のもの。

色々な「ひょうちゃん」が発表されていて、コレクターも多いのだそうです。
えぇ、ただこれだけで・・・落ちなんてありませんが・・・何か?
勿論大変おいしくいただきましたよ。
で、食べながら思ったんですが・・・これの正式な呼び方って・・・シウマイ?
賢パパはもちろん崎陽軒の呼び方に倣ってシウマイと呼ばせていただいておりますが・・・
中華食堂のメニューなんかを見るとシュウマイ、あるいはシューマイなんてのも目にします。
まぁ、例によって調べてみたんですが・・・・シウマイというのは崎陽軒さんの命名らしいですねぇ。
ついでですが、こんなどうでもいいようなことを真面目に議論している方がいるんですわ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11814071
所詮は外国の食べ物で外国語の呼び方を日本人の耳で聞くわけですから正確な発音なんて再現する方が無理というものなんですよねぇ。
そんな事よりも面白い項目を見つけましたよ。
上の写真の手前に写っている物体なんですが・・・なんだかおわかりでしょうか?
これ、シウマイについている醤油入れなんですが、ちゃんと「ひょうちゃん」と言う名前がついてるんですってねぇ。
昭和30年代と言いますから賢パパが小学生の頃かも知れませんがこれが初代の「ひょうちゃん」だそうです。

昭和63年には2代目が登場して

平成17年、18年のクリスマス限定バージョンも

最新は平成20年の100周年記念のもの。

色々な「ひょうちゃん」が発表されていて、コレクターも多いのだそうです。
えぇ、ただこれだけで・・・落ちなんてありませんが・・・何か?
2011年09月08日
PPK
ここのところめっきり涼しくなりまして・・・寒くて夜中に目が覚めてタオルケットを掛けて寝なおす日が続いております。
さて、今日のタイトルですが、なんだかおわかりですか・・・PPK?
賢パパの若い頃ブレークしたフォークソングのグループ・・・?
あれはPPM・・・

PPKとは・・・次の説明をどうぞ。
ピンピン・コロリをローマ字書きして、その頭文字をつなげたもの。
高齢者の「元気に生きて死ぬときはコロリと死にたい」という願望を表現している。
長患いをしないで、寿命と健康寿命(平均寿命とは別に、高齢者が病気をしないで健康で生活できる期間を指す)の差を縮めようということである。
長野県内で中高年の健康づくりのキャッチフレーズとして使われたのが始まりで、その語呂のよさからしだいに全国に広まっている。
長野県は、高齢者1人あたりの医療費が全国でもっとも低い。
国民健康保険中央会が設置した研究会によれば、農作業などで体を動かす、食生活の改善、保健や医療の充実、などが要因として考えられるという。
こうした高齢者なら寝たきりにならず、平均寿命と健康寿命との差もなく天寿を全うできるかもしれない。
そして、その元気なお年寄りが多いという長野県佐久市には「ぴんころ地蔵」なるお地蔵さんがあるのだとか・・・・

2003年(平成15年)9月に建立されたのだそうです。
何とも有難いお地蔵さんじゃありませんかねぇ~。
おっと、これだけでは終わりませんよ。
他にも「ぴんころ地蔵」がないかと調べてみたんですわ。
すると・・・こんなのがありました。

茨城県の水戸市にある「保和院」桂岸寺には宝暦年間(1750年頃)に建てられた延命地蔵尊が祀られていて古来から天命を全うし、ころりと最期を迎える功徳があるとされ、“ぴんころ地蔵さん”として親しまれて来たのだそうです。
近年、自分の体の病めるところと延命地蔵さんの同じところに直接触れて願い事ができる小さなお地蔵さんを望む声が聞かれるようになり、この願いを叶える新しい延命地蔵尊を、2007年に旧来の延命地蔵尊の並びに建立したのだとか。
更に調べてみると・・・・こんなのも見つかりましたよ。

2007年7月、マロニエ下呂温泉20周年記念事業として建立されたと言いますから水戸のものと同じくらいの時期に作られたものでしょうかね。
でも・・・・これって佐久のお地蔵さんと全く同じポーズじゃありませんか!
何かの商品のデザインだったら「意匠権」の問題で一悶着ありそうですが・・・・さすがにお地蔵さんだけあって・・・心が広いのでしょうねぇ。
さて、今日のタイトルですが、なんだかおわかりですか・・・PPK?
賢パパの若い頃ブレークしたフォークソングのグループ・・・?
あれはPPM・・・

PPKとは・・・次の説明をどうぞ。
ピンピン・コロリをローマ字書きして、その頭文字をつなげたもの。
高齢者の「元気に生きて死ぬときはコロリと死にたい」という願望を表現している。
長患いをしないで、寿命と健康寿命(平均寿命とは別に、高齢者が病気をしないで健康で生活できる期間を指す)の差を縮めようということである。
長野県内で中高年の健康づくりのキャッチフレーズとして使われたのが始まりで、その語呂のよさからしだいに全国に広まっている。
長野県は、高齢者1人あたりの医療費が全国でもっとも低い。
国民健康保険中央会が設置した研究会によれば、農作業などで体を動かす、食生活の改善、保健や医療の充実、などが要因として考えられるという。
こうした高齢者なら寝たきりにならず、平均寿命と健康寿命との差もなく天寿を全うできるかもしれない。
そして、その元気なお年寄りが多いという長野県佐久市には「ぴんころ地蔵」なるお地蔵さんがあるのだとか・・・・

2003年(平成15年)9月に建立されたのだそうです。
何とも有難いお地蔵さんじゃありませんかねぇ~。
おっと、これだけでは終わりませんよ。
他にも「ぴんころ地蔵」がないかと調べてみたんですわ。
すると・・・こんなのがありました。

茨城県の水戸市にある「保和院」桂岸寺には宝暦年間(1750年頃)に建てられた延命地蔵尊が祀られていて古来から天命を全うし、ころりと最期を迎える功徳があるとされ、“ぴんころ地蔵さん”として親しまれて来たのだそうです。
近年、自分の体の病めるところと延命地蔵さんの同じところに直接触れて願い事ができる小さなお地蔵さんを望む声が聞かれるようになり、この願いを叶える新しい延命地蔵尊を、2007年に旧来の延命地蔵尊の並びに建立したのだとか。
更に調べてみると・・・・こんなのも見つかりましたよ。

2007年7月、マロニエ下呂温泉20周年記念事業として建立されたと言いますから水戸のものと同じくらいの時期に作られたものでしょうかね。
でも・・・・これって佐久のお地蔵さんと全く同じポーズじゃありませんか!
何かの商品のデザインだったら「意匠権」の問題で一悶着ありそうですが・・・・さすがにお地蔵さんだけあって・・・心が広いのでしょうねぇ。
2011年09月07日
温暖化の証明(植物編)
サッカー男子はなでしこのように連勝とは行きませんでしたが、敵地でゲットした勝ち点1は貴重ですから・・・次からに期待したいと思います。
さて、以前に温暖化とクマゼミの分布の変化について書いたことがありますが、今日はその「植物編」です。
もうすでに終わりかけていますが皆さんの住んでいる地方でこんな花を見かけることはありませんか?

アップで見ると

ちょっと見はテッポウユリに似ていますが・・「タカサゴユリ」という名前のユリなんです。
実はこのユリ「帰化植物」と言って元々我が国にはなかったのが外国から入って来ていつの間にか大きな顔でなわばりを広げているのです。
帰化植物についてもう少し説明を加えておきますと、単に国外から入った植物の意味ではなく、人為的な手段で持ち込まれた植物のうちで、野外で勝手に生育するようになったもののことだそうです。
で、タカサゴユリに話を戻しますが台湾原産のユリで遠く戦前に観賞用として持ち込まれたのが始まりのようですねぇ。
台湾が原産ということは暖かい地方が生育に適していると思われますが近年当地においては至る所で目にするようになっています。
賢パパが初めてこの花を見たのは今から約20年も前の事でしたが、当時はあっちの空き地に一株、こっちの道端に一株と言う感じで冒頭の写真のような群落にお目にかかることはありませんでした。
今ではどこの庭先や道端、空き地でも目にすることが出来るようになりましたから・・・やはり温暖化が進んでいる証拠なんでしょうかねぇ。
さて、以前に温暖化とクマゼミの分布の変化について書いたことがありますが、今日はその「植物編」です。
もうすでに終わりかけていますが皆さんの住んでいる地方でこんな花を見かけることはありませんか?
アップで見ると

ちょっと見はテッポウユリに似ていますが・・「タカサゴユリ」という名前のユリなんです。
実はこのユリ「帰化植物」と言って元々我が国にはなかったのが外国から入って来ていつの間にか大きな顔でなわばりを広げているのです。
帰化植物についてもう少し説明を加えておきますと、単に国外から入った植物の意味ではなく、人為的な手段で持ち込まれた植物のうちで、野外で勝手に生育するようになったもののことだそうです。
で、タカサゴユリに話を戻しますが台湾原産のユリで遠く戦前に観賞用として持ち込まれたのが始まりのようですねぇ。
台湾が原産ということは暖かい地方が生育に適していると思われますが近年当地においては至る所で目にするようになっています。
賢パパが初めてこの花を見たのは今から約20年も前の事でしたが、当時はあっちの空き地に一株、こっちの道端に一株と言う感じで冒頭の写真のような群落にお目にかかることはありませんでした。
今ではどこの庭先や道端、空き地でも目にすることが出来るようになりましたから・・・やはり温暖化が進んでいる証拠なんでしょうかねぇ。
2011年09月05日
避難指示と避難勧告
スピードが遅かったため、記録的な降水量となり、各地に大きな被害をもたらした今回の台風12号(タラス)でしたが何とか去って行きました。
台風一過・・・と言うと次に続くのは「青空」がお決まりのはずなんですが・・・どういうわけかまだ降っていますねぇ。
日曜日に賢パパが計画していた富士登山はもちろんキャンセル。
降り続く雨のおかげで外に出ることが出来ず・・・テレビとPCだけの土日でした。
で、テレビを観ていると嫌でも目に入るのが台風関連のニュースです。
河川の氾濫によって一面海のような被災地の画像とともに映し出されるのが・・・O山県T野市の全住民に避難勧告とか・・・M重県O鷲市に避難指示というテロップです。
最初のうちは何気に見ていた賢パパですが・・・・だんだん気になることがありまして・・・
それは「避難勧告」と「避難指示」の違いなんですが、一体どんな風に決められているんだろう・・・?
どうせ何もすることがありませんから、早速調べてみます。
すると・・・


「避難命令」なんて言葉を耳にしたこともあるような気がするんですが・・・法律で規定しているのは「勧告」と「指示」の2種類だけなんだそうです。
「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』で、その内容は「避難のための立ち退きの勧告」。
一方、、「避難指示」を規定している法律は前述の、『災害対策基本法』のほか、『水防法』、『地すべり等防止法』、『警察官職務執行法』、『自衛隊法』で、その内容は「避難のための立ち退きの指示」と言うことになります。
いずれの規定についても強制力ないそうですが・・・そういえば多くの住民が避難所に避難しているのに・・・避難しないで自宅におられる方がテレビに映ってるのを見かけることがありますよねぇ。
なんだかオチのない話になってしまってすみません。
台風一過・・・と言うと次に続くのは「青空」がお決まりのはずなんですが・・・どういうわけかまだ降っていますねぇ。
日曜日に賢パパが計画していた富士登山はもちろんキャンセル。
降り続く雨のおかげで外に出ることが出来ず・・・テレビとPCだけの土日でした。
で、テレビを観ていると嫌でも目に入るのが台風関連のニュースです。
河川の氾濫によって一面海のような被災地の画像とともに映し出されるのが・・・O山県T野市の全住民に避難勧告とか・・・M重県O鷲市に避難指示というテロップです。
最初のうちは何気に見ていた賢パパですが・・・・だんだん気になることがありまして・・・
それは「避難勧告」と「避難指示」の違いなんですが、一体どんな風に決められているんだろう・・・?
どうせ何もすることがありませんから、早速調べてみます。
すると・・・
「避難命令」なんて言葉を耳にしたこともあるような気がするんですが・・・法律で規定しているのは「勧告」と「指示」の2種類だけなんだそうです。
「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』で、その内容は「避難のための立ち退きの勧告」。
一方、、「避難指示」を規定している法律は前述の、『災害対策基本法』のほか、『水防法』、『地すべり等防止法』、『警察官職務執行法』、『自衛隊法』で、その内容は「避難のための立ち退きの指示」と言うことになります。
いずれの規定についても強制力ないそうですが・・・そういえば多くの住民が避難所に避難しているのに・・・避難しないで自宅におられる方がテレビに映ってるのを見かけることがありますよねぇ。
なんだかオチのない話になってしまってすみません。
2011年09月01日
荒唐無稽
あっという間に8月が終わり、今日からはもう9月に入りましたねぇ。
少しは涼しくなると良いのですが、台風の接近なんてニュースにはちょっと心配させられます。
さて、最近、4字熟語のおさらいをしている賢パパでありまして・・・
ブログのネタにも使わせていただいておりますが・・・せっかくの機会なので皆さんも一緒におさらいをしませんか?
と言うことで今日の話題は「荒唐無稽」の4字熟語です。
意味はですねぇ、「言葉や説明に根拠がなく、ばかげていること。でたらめであること。」
賢パパもあんまり適当なことばかり書いてると「荒唐無稽」なんて指摘を受けないとも限りませんから・・・少しは考えて書いて行く事を心がけたいと思います。
で、今日の4字熟語問題です。
今日は自虐ネタです。
この写真が表している4字熟語を当ててください。

勿論ギャグですから・・・
賢パパの頭の写真なんですが、撮ったのを見てから元々考えていた字を他の字に差し替えました。
読みは同じなんですが・・・・断然差し替え後の方がインパクトあります。
少しは涼しくなると良いのですが、台風の接近なんてニュースにはちょっと心配させられます。
さて、最近、4字熟語のおさらいをしている賢パパでありまして・・・
ブログのネタにも使わせていただいておりますが・・・せっかくの機会なので皆さんも一緒におさらいをしませんか?
と言うことで今日の話題は「荒唐無稽」の4字熟語です。
意味はですねぇ、「言葉や説明に根拠がなく、ばかげていること。でたらめであること。」
賢パパもあんまり適当なことばかり書いてると「荒唐無稽」なんて指摘を受けないとも限りませんから・・・少しは考えて書いて行く事を心がけたいと思います。
で、今日の4字熟語問題です。
今日は自虐ネタです。
この写真が表している4字熟語を当ててください。
勿論ギャグですから・・・
賢パパの頭の写真なんですが、撮ったのを見てから元々考えていた字を他の字に差し替えました。
読みは同じなんですが・・・・断然差し替え後の方がインパクトあります。
2011年08月28日
4字熟語
作日の「山頂ポーズ研究会」のブログに書いたポーズの事なんですが・・・・今までは「シェ~」とか「クエックエッ」とか・・・既にメジャーになっているポーズをお借りして・・・それをそのまま再現してパチリと写真を撮っていたんです。
それが・・・ゼロ富士トレーニングでしばらくポーズから遠ざかっていたこともあり・・・・もう一度山頂ポーズの意義を考え直してみたのです。
すると、そうだ、出来合いのポーズも良いが自分だけのオリジナルポーズを作ってそれを画像で残したら・・・もっともっと意義深い山歩きになるに違いない。
そう思った賢パパは早速オリジナルポーズの作成に取り掛かりました。
しかし・・・悲しいかな、いきなりポーズが頭に浮かぶはずもありません。
そこで賢パパは考えました。
「何かのパロディでポーズを作ってみたらどうだろう?」
で、さんざん考えた挙句に思いついたのが・・・4字熟語のパロディでした。
最近、4字熟語をおさらいしていることもあって・・・・何とかポーズと結びつけることが出来そうです。
そんなことでしばらくの間は4字熟語と山頂ポーズにおつきあいいただくことになると思いますがよろしくお願いいたします。
というわけで・・・早速パロディ4字熟語です。
これはポーズではありませんが例題として解いてみてくださいね。
次の2枚の画像から思い浮かぶ超一般的なな4字熟語はなんでしょうか?


あっ、大サービスでヒント出しちゃいますが・・・枡は一合の枡です。
これは超簡単な例題ですが・・・・次回からは少しずつ難しくなって行きますよ。
昨日は山歩きして・・・ポーズ写真をたくさん撮って来ようと思っていましたが・・・・天気は今日の方が良さそうなので、一日延期してこれから歩いて来ることにしました。
山頂ポーズてんこ盛りの山歩きになりそうですねぇ~。
それが・・・ゼロ富士トレーニングでしばらくポーズから遠ざかっていたこともあり・・・・もう一度山頂ポーズの意義を考え直してみたのです。
すると、そうだ、出来合いのポーズも良いが自分だけのオリジナルポーズを作ってそれを画像で残したら・・・もっともっと意義深い山歩きになるに違いない。
そう思った賢パパは早速オリジナルポーズの作成に取り掛かりました。
しかし・・・悲しいかな、いきなりポーズが頭に浮かぶはずもありません。
そこで賢パパは考えました。
「何かのパロディでポーズを作ってみたらどうだろう?」
で、さんざん考えた挙句に思いついたのが・・・4字熟語のパロディでした。
最近、4字熟語をおさらいしていることもあって・・・・何とかポーズと結びつけることが出来そうです。
そんなことでしばらくの間は4字熟語と山頂ポーズにおつきあいいただくことになると思いますがよろしくお願いいたします。
というわけで・・・早速パロディ4字熟語です。
これはポーズではありませんが例題として解いてみてくださいね。
次の2枚の画像から思い浮かぶ超一般的なな4字熟語はなんでしょうか?


あっ、大サービスでヒント出しちゃいますが・・・枡は一合の枡です。
これは超簡単な例題ですが・・・・次回からは少しずつ難しくなって行きますよ。
昨日は山歩きして・・・ポーズ写真をたくさん撮って来ようと思っていましたが・・・・天気は今日の方が良さそうなので、一日延期してこれから歩いて来ることにしました。
山頂ポーズてんこ盛りの山歩きになりそうですねぇ~。
2011年08月23日
ドクターフィッシュ
いやぁ~、先週までの暑さは何だったのでしょうかねぇ・・・
今朝なんて肌寒いぐらいの涼しさですよ。
このまま秋になってくれれば良いと思ったら・・・明日からは又30℃超えの日が戻って来るようですねぇ。
さて、先日の駿河健康ランドでのお泊り飲み会の時の事なんですが・・・
駐車場から連絡通路を通って館内に入り履物入れの所に行こうと思って何気に目をやると・・・こんな看板が。

おぉ、そう言えばここの名物のひとつになっていましたっけねぇ~。
確か掃除魚って言うんじゃなかったかなぁと思って調べてみると
掃除魚(そうじうお、Cleaner fishes)とは、他種の魚の死んだ皮膚組織や外部寄生虫を食べる習性をもつ魚類の総称。これは双方が利益を得る生態学的相互作用、すなわち相利共生の一例として理解されている。
ベラ・ハゼ・シクリッド・ナマズなど、さまざまな魚が掃除行動をすることが知られている。
掃除魚と言うと範囲が広すぎるようですね。
で、もうちょっと調べてみると・・・
ドクターフィッシュ(Doctor fish, 学名 Garra rufa)は、コイ科の魚ガラ・ルファの通称。
分布 [編集]
トルコ、イラン、イラク、シリア、レバノン周辺の西アジア地域の河川。
生態 [編集]
全長約10cm。西アジアの河川域に生息する淡水魚で、37℃程度の高い水温でも生息できるためトルコなどの温泉にも生息するが通常は河川や池沼に生息する。水温、水質ともに適応の幅が非常に広く丈夫な魚である。餌を求める時は活発に動き回るが、普段は石などの上や陰でじっとしていることが多い。食性は雑食性。口が吸盤のようになっており石や岩などに付着した藻類を舐めるようにして食べることができるほか、底にいる微生物や昆虫の幼虫などを食べる。
幼魚の頃は群れで生活するが、成長するとオスは縄張りを持つようになり多少攻撃的な性格にかわる。繁殖は卵生で水草やコケを産卵床とし直径2-3mmの卵を産む。孵化までの期間は水温により異なるものの、25度前後の水温でおおむね3-5日程度で5mm前後の稚魚が孵化する。
ドクターフィッシュの由来 [編集]
温泉に入ったヒトの古くなった角質を食べる習性があり、歯が無いため肌を傷つける事なくアトピー性皮膚炎・乾癬など皮膚病に治療効果があるとされ、「ドクターフィッシュ」の通称で知られる。ドイツやトルコではドクターフィッシュによる治療が保険適用の医療行為として認められている。ヒトの角質を食べるのは、温泉では他の生物があまり生息せず、他に食べるものが無いため、と考えられている。従って、えさが豊富にある環境下であれば人の角質を食べることはほとんどない。寿命はだいたい7年、角質を食べるのは生後2ヶ月から2年半ごろまでである。
近年、日本でも皮膚病の治療効果が注目され、日帰り入浴施設などで「フィッシュセラピー」としてのサービスが提供されている。
掃除魚と言うよりもドクターフィッシュと呼ぶ方がかっこいいですもんねぇ。
ということで、残念ながらこの日はお休みでしたが・・・・これがドクターフィッシュの写真だそうです。

今夜は本当に久しぶりで「はなの舞」です。
先月の「海からの宝永山」の反省会と今後の活動計画についての話し合いです。
早く涼しくなりませんかねぇ~。
今朝なんて肌寒いぐらいの涼しさですよ。
このまま秋になってくれれば良いと思ったら・・・明日からは又30℃超えの日が戻って来るようですねぇ。
さて、先日の駿河健康ランドでのお泊り飲み会の時の事なんですが・・・
駐車場から連絡通路を通って館内に入り履物入れの所に行こうと思って何気に目をやると・・・こんな看板が。
おぉ、そう言えばここの名物のひとつになっていましたっけねぇ~。
確か掃除魚って言うんじゃなかったかなぁと思って調べてみると
掃除魚(そうじうお、Cleaner fishes)とは、他種の魚の死んだ皮膚組織や外部寄生虫を食べる習性をもつ魚類の総称。これは双方が利益を得る生態学的相互作用、すなわち相利共生の一例として理解されている。
ベラ・ハゼ・シクリッド・ナマズなど、さまざまな魚が掃除行動をすることが知られている。
掃除魚と言うと範囲が広すぎるようですね。
で、もうちょっと調べてみると・・・
ドクターフィッシュ(Doctor fish, 学名 Garra rufa)は、コイ科の魚ガラ・ルファの通称。
分布 [編集]
トルコ、イラン、イラク、シリア、レバノン周辺の西アジア地域の河川。
生態 [編集]
全長約10cm。西アジアの河川域に生息する淡水魚で、37℃程度の高い水温でも生息できるためトルコなどの温泉にも生息するが通常は河川や池沼に生息する。水温、水質ともに適応の幅が非常に広く丈夫な魚である。餌を求める時は活発に動き回るが、普段は石などの上や陰でじっとしていることが多い。食性は雑食性。口が吸盤のようになっており石や岩などに付着した藻類を舐めるようにして食べることができるほか、底にいる微生物や昆虫の幼虫などを食べる。
幼魚の頃は群れで生活するが、成長するとオスは縄張りを持つようになり多少攻撃的な性格にかわる。繁殖は卵生で水草やコケを産卵床とし直径2-3mmの卵を産む。孵化までの期間は水温により異なるものの、25度前後の水温でおおむね3-5日程度で5mm前後の稚魚が孵化する。
ドクターフィッシュの由来 [編集]
温泉に入ったヒトの古くなった角質を食べる習性があり、歯が無いため肌を傷つける事なくアトピー性皮膚炎・乾癬など皮膚病に治療効果があるとされ、「ドクターフィッシュ」の通称で知られる。ドイツやトルコではドクターフィッシュによる治療が保険適用の医療行為として認められている。ヒトの角質を食べるのは、温泉では他の生物があまり生息せず、他に食べるものが無いため、と考えられている。従って、えさが豊富にある環境下であれば人の角質を食べることはほとんどない。寿命はだいたい7年、角質を食べるのは生後2ヶ月から2年半ごろまでである。
近年、日本でも皮膚病の治療効果が注目され、日帰り入浴施設などで「フィッシュセラピー」としてのサービスが提供されている。
掃除魚と言うよりもドクターフィッシュと呼ぶ方がかっこいいですもんねぇ。
ということで、残念ながらこの日はお休みでしたが・・・・これがドクターフィッシュの写真だそうです。

今夜は本当に久しぶりで「はなの舞」です。
先月の「海からの宝永山」の反省会と今後の活動計画についての話し合いです。
早く涼しくなりませんかねぇ~。
2011年08月13日
ピーカングッズ
その昔、富士山のふもとに絶世の美女が住んでいたそうな。
その美女の名は・・・・言えませんが・・・とにかく美女で・・・その上多芸。
天は二物を与え賜わず・・・なんて言いますが・・・あれは嘘ですな。
その昔、賢パパの家で飲み会をやった時に・・・賢パパの晴れ男ぶりを話して聞かせると・・・即座にこんなグッズを作ってしまったのでありますよ。


これがすなわち「ピーカンお札(お守り?)」というわけです。
これのご利益がどんなものだったかは・・・手にした多くの方々が身を以て体験したことなのでここでは多くを語りますまい。
しか~し、これが作られたのが2007年の10月。
そろそろ4年になろうとしております。
来月、所持者の多くが一堂に会する機会がありまして・・・・この機会にリニューアルをとの提案が・・・制作者からありました。
それは良い考えだと一も二もなく賛同したのは言うまでもありません。
そして・・・ニューバージョンとして生まれ変わったのがこれ。




どうです、素晴らしい出来栄えじゃありませんか!
後は賢パパが「入魂の儀」を厳かに執り行って・・・めでたく完成の運びとなります。
そして来月の某日、山梨県の某所で行われる大宴会の席上で参加者の皆さんの中の希望者に配られるというわけです。
で、ここで賢パパから一つ提案があります。
これだけのものを作るにはそれなりの費用が掛かっていると思うんです。
せめて部材代ぐらいを負担してあげるというのはどうでしょうかねぇ?
その美女の名は・・・・言えませんが・・・とにかく美女で・・・その上多芸。
天は二物を与え賜わず・・・なんて言いますが・・・あれは嘘ですな。
その昔、賢パパの家で飲み会をやった時に・・・賢パパの晴れ男ぶりを話して聞かせると・・・即座にこんなグッズを作ってしまったのでありますよ。
これがすなわち「ピーカンお札(お守り?)」というわけです。
これのご利益がどんなものだったかは・・・手にした多くの方々が身を以て体験したことなのでここでは多くを語りますまい。
しか~し、これが作られたのが2007年の10月。
そろそろ4年になろうとしております。
来月、所持者の多くが一堂に会する機会がありまして・・・・この機会にリニューアルをとの提案が・・・制作者からありました。
それは良い考えだと一も二もなく賛同したのは言うまでもありません。
そして・・・ニューバージョンとして生まれ変わったのがこれ。
どうです、素晴らしい出来栄えじゃありませんか!
後は賢パパが「入魂の儀」を厳かに執り行って・・・めでたく完成の運びとなります。
そして来月の某日、山梨県の某所で行われる大宴会の席上で参加者の皆さんの中の希望者に配られるというわけです。
で、ここで賢パパから一つ提案があります。
これだけのものを作るにはそれなりの費用が掛かっていると思うんです。
せめて部材代ぐらいを負担してあげるというのはどうでしょうかねぇ?
2011年08月12日
犬の熱中症
今年の夏は節電の夏ですよねぇ。
で、あまりの暑さに人間だけではなく、熱中症にかかるペットが急増しているというニュースがありました。
ある動物病院の関係者にによりますと
「うちの病院でいうと、今年は前年比2割増しくらいです。特に多いのは犬ですね。猫はもともと砂漠の動物ともいわれていて、暑さや渇きに強いのですが、犬は冷涼な地域の出身種が多く、暑さに弱いんです」。
他にも、犬が熱中症になりやすいのにはこんな理由があるんだそうです。
「人間は、汗腺があって熱を放出できますが、犬の場合は口からハァハァと呼吸するか、四肢の肉球で汗を出すしかないので、非常に体温調節がしづらいんです。それに人間より体が地面に近いので、地面からの反射熱も受けやすくなります」(同病院関係者)
夏場のアスファルトは、昼間だと50度を超える熱さになるので地面に近いだけにその影響は大きく、そのまま歩かせると熱中症だけではなく、肉球を火傷する危険性もあると言います。
特に熱中症にかかりやすいのは、短頭種といって鼻の短い犬種なんだそうです。
「気道が短かったり、曲がっているため、換気が難しくなりやすいんです。シーズー、チン、ペキニーズ、フレンチブルドッグなど、いま人気の犬種は要注意ですね」(同関係者)
これがシーズーで

これがフレンチブルドッグです。

なるほど鼻が短いですねぇ。
それに比べたらうちの賢なんて・・・こうですから

鼻は短くありません。
では年齢が関係あるのかと言いますと・・・・
「犬の場合、5才を超えると人間でいう35才を過ぎた中年で、熱中症に限らず日々の健康管理が重要になります。ぐったりしていても、熱中症なのか持病なのかわからない場合は、早めに獣医師に相談してください。5才以上の犬は、年2回以上、健康診断を受けたほうがいいですね」(同関係者)
健康診断を受けた方が良いなんて・・・しっかり商売のPRをしていますが、5歳以上はともかく賢なんてもう9歳ですから・・・健康診断は毎年受診していますよ。
さて、犬の熱中症とは何の関係もありませんが・・・今日は先月の富士山涙の敗退以来1か月ぶりで山歩きをして来ようと思っています。
低山なので涼しくはないと思いますが風でも吹いてくれればそんなに暑くはないと思います。
天気が良ければ富士山や南アルプスが見えるんですが・・・どうでしょうかねぇ。
結果は明日のブログで・・・・
で、あまりの暑さに人間だけではなく、熱中症にかかるペットが急増しているというニュースがありました。
ある動物病院の関係者にによりますと
「うちの病院でいうと、今年は前年比2割増しくらいです。特に多いのは犬ですね。猫はもともと砂漠の動物ともいわれていて、暑さや渇きに強いのですが、犬は冷涼な地域の出身種が多く、暑さに弱いんです」。
他にも、犬が熱中症になりやすいのにはこんな理由があるんだそうです。
「人間は、汗腺があって熱を放出できますが、犬の場合は口からハァハァと呼吸するか、四肢の肉球で汗を出すしかないので、非常に体温調節がしづらいんです。それに人間より体が地面に近いので、地面からの反射熱も受けやすくなります」(同病院関係者)
夏場のアスファルトは、昼間だと50度を超える熱さになるので地面に近いだけにその影響は大きく、そのまま歩かせると熱中症だけではなく、肉球を火傷する危険性もあると言います。
特に熱中症にかかりやすいのは、短頭種といって鼻の短い犬種なんだそうです。
「気道が短かったり、曲がっているため、換気が難しくなりやすいんです。シーズー、チン、ペキニーズ、フレンチブルドッグなど、いま人気の犬種は要注意ですね」(同関係者)
これがシーズーで

これがフレンチブルドッグです。

なるほど鼻が短いですねぇ。
それに比べたらうちの賢なんて・・・こうですから
鼻は短くありません。
では年齢が関係あるのかと言いますと・・・・
「犬の場合、5才を超えると人間でいう35才を過ぎた中年で、熱中症に限らず日々の健康管理が重要になります。ぐったりしていても、熱中症なのか持病なのかわからない場合は、早めに獣医師に相談してください。5才以上の犬は、年2回以上、健康診断を受けたほうがいいですね」(同関係者)
健康診断を受けた方が良いなんて・・・しっかり商売のPRをしていますが、5歳以上はともかく賢なんてもう9歳ですから・・・健康診断は毎年受診していますよ。
さて、犬の熱中症とは何の関係もありませんが・・・今日は先月の富士山涙の敗退以来1か月ぶりで山歩きをして来ようと思っています。
低山なので涼しくはないと思いますが風でも吹いてくれればそんなに暑くはないと思います。
天気が良ければ富士山や南アルプスが見えるんですが・・・どうでしょうかねぇ。
結果は明日のブログで・・・・
2011年08月05日
温暖化の証明
毎年この時期になるとうんざりさせられるのが「シャンシャンシャンシャン・・・」とやかましいあの声です。
恋に焦がれて鳴くセミよりも鳴かぬホタルが身を焦がす・・・なんて都都逸があるぐらいですから、やっぱりあれはメスに対してオスが自分をアピールしているんでしょうねぇ。
さて、本題です。
このセミが鳴く頃になると気になるのが地球温暖化のこと。

どうしてセミと温暖化?と思われる方もおられるとは思いますが・・・
実はこのクマゼミってセミは昔からの生息域が関東南部、東海、北陸地方と西日本(近畿、中国、四国、九州、南西諸島)などの温暖な地域なんです。
だから温暖化によって気温が上がればクマゼミの分布も北へと広がって行くと・・・誰でも思いますよねぇ。
ところがです、そう簡単には行かないらしくて・・・・
千葉県の房総半島の南部には昔から生息している場所があるようなんです。
房総半島の南部に行くためにはどうしたって房総半島の北部を経由しなくてはいけませんから、そこにも生息していなくてはなりません。
それなのに北部には生息していないんですからこう考えるのが自然なようです。
つまり、大昔の温暖期にクマゼミは南関東の広域で生息していたが、寒冷期になって南関東の大部分でクマゼミが死滅、冬でも比較的温暖な房総半島南部や三浦半島南端のみ(特に城ヶ島)に生き残るだけとなったのだろうと・・・・
話が横道にそれました。
ここで房総半島南部の特異性に触れていると話が面倒になるので・・・単純に北上の話に戻します。
生き物は生育に適した土地を求めてそのテリトリーを広げようとする本能がありますから、クマゼミだって例外ではありません。
それなら生息に適した環境の中で目いっぱいテリトリーを広げて行きます。
すなわち生育に適した温度の地域が広がればその限界まで進出して行くのが習性というものですよねぇ。
だから・・・・平均気温が上がればクマゼミの生息域は北に向かって広がろうというものなんですね。
そうなると今までは千葉県あたりが生息の北限だったのが茨城や埼玉、栃木と広がって行きますよねぇ。
賢パパが大学を卒業して横浜に出て来た40年前には横浜でクマゼミを見たことなんてありませんでした。
それが、今では普通に鳴いていると聞きます。
一体どこまで北上しているのか・・・とても興味があるんです。
この記事を読まれた関東以北にお住いの方でクマゼミの姿を見たり鳴き声を聞いたことのある方は是非コメントをお寄せください。
お願いします。
さて、賢パパですが・・・今日は本当にクマゼミが生息するのかを確かめるため横浜に行って来ますよ。
恋に焦がれて鳴くセミよりも鳴かぬホタルが身を焦がす・・・なんて都都逸があるぐらいですから、やっぱりあれはメスに対してオスが自分をアピールしているんでしょうねぇ。
さて、本題です。
このセミが鳴く頃になると気になるのが地球温暖化のこと。

どうしてセミと温暖化?と思われる方もおられるとは思いますが・・・
実はこのクマゼミってセミは昔からの生息域が関東南部、東海、北陸地方と西日本(近畿、中国、四国、九州、南西諸島)などの温暖な地域なんです。
だから温暖化によって気温が上がればクマゼミの分布も北へと広がって行くと・・・誰でも思いますよねぇ。
ところがです、そう簡単には行かないらしくて・・・・
千葉県の房総半島の南部には昔から生息している場所があるようなんです。
房総半島の南部に行くためにはどうしたって房総半島の北部を経由しなくてはいけませんから、そこにも生息していなくてはなりません。
それなのに北部には生息していないんですからこう考えるのが自然なようです。
つまり、大昔の温暖期にクマゼミは南関東の広域で生息していたが、寒冷期になって南関東の大部分でクマゼミが死滅、冬でも比較的温暖な房総半島南部や三浦半島南端のみ(特に城ヶ島)に生き残るだけとなったのだろうと・・・・
話が横道にそれました。
ここで房総半島南部の特異性に触れていると話が面倒になるので・・・単純に北上の話に戻します。
生き物は生育に適した土地を求めてそのテリトリーを広げようとする本能がありますから、クマゼミだって例外ではありません。
それなら生息に適した環境の中で目いっぱいテリトリーを広げて行きます。
すなわち生育に適した温度の地域が広がればその限界まで進出して行くのが習性というものですよねぇ。
だから・・・・平均気温が上がればクマゼミの生息域は北に向かって広がろうというものなんですね。
そうなると今までは千葉県あたりが生息の北限だったのが茨城や埼玉、栃木と広がって行きますよねぇ。
賢パパが大学を卒業して横浜に出て来た40年前には横浜でクマゼミを見たことなんてありませんでした。
それが、今では普通に鳴いていると聞きます。
一体どこまで北上しているのか・・・とても興味があるんです。
この記事を読まれた関東以北にお住いの方でクマゼミの姿を見たり鳴き声を聞いたことのある方は是非コメントをお寄せください。
お願いします。
さて、賢パパですが・・・今日は本当にクマゼミが生息するのかを確かめるため横浜に行って来ますよ。
2011年07月27日
卵とじうどんとワンタンメン
おととい、やっと待ちに待ったニューPCが来たのですが・・・・インターネットに接続することが出来なくて・・・
昨夜色々とやってみましたが・・・ダメ。
で、先ほど会社から帰って来て・・・テクニカルセンターの方に教えていただいて・・・めでたく接続が完了です。
あ、電子メールのほうはまだ接続出来ていませんので・・・メールを読むことは出来ません。
ニューPCからの記念すべき第一弾です。
さて、もうずいぶん昔の事なのではっきりしたことは憶えていないのですが・・・
30年以上も前に仕事で神戸に行った時に・・・こんな事がありました。
神戸と言えば勿論「神戸牛」ですから・・・同じ地区に出張していた友達と一緒に・・・・鉄板焼きかなんかで神戸牛を堪能した後・・・友達と別れて宿泊先のホテルに帰ろうとしたんですが・・・
肉ってやつはすぐにお腹が一杯になるんですが・・・減るのも速いんです。
で、歩いていると・・・タイミング良くうどん屋さんの看板が目に入ります。
中に入ってビールを一本注文して・・・運ばれて来る間に食べるものをメニューから選びます。
ビールを運んで来てくれたのは歳の行ったこの店のおかみさんでしょうかねぇ。
賢パパが注文したのは「卵とじうどん」なんですが・・・「ネギを入れないで・・・」って注文をつけたんです。
おかみさんは厨房へ行って調理をしているご主人にその旨を伝えます。
するとご主人が何やら文句を言っています。
初めは気にも留めずにビールを飲んでいたのですが・・・言い争う声が次第に大きくなるので・・・嫌でも耳に入って来てしまいます。
どうやら賢パパが注文した卵とじうどんが言い争いの原因のようです。
主人「卵でネギをとじるから卵とじやないかっ!」
おかみさん「そんなこと言うたかて、入れんでええゆうとるんやから・・・」
主人「それじゃ卵とじやないわ!」
おかみさん「お客さんがそれでええゆうとるんやから・・・」
たまりかねた賢パパはご主人に謝って・・・・出来て来たのは

半泣き状態で食べましたわ。
それ以来、賢パパは卵とじうどんというものを食べたことがありません。
その20年後ぐらいに、今度はいわき市に出張した時の話ですが・・・
昼飯をラーメン屋さんで食べたのですが、当然ビールと餃子を頂きますから・・・・麺類は軽くてもOKです。
賢パパ、ラーメンはふるさとの白河ラーメンしか食べませんから・・・こういう時は大抵「ワンタン」を注文します。
で、この時もワンタンを頼んだのですが・・・出来上がろうかという頃合いになって・・・厨房の中で言い争いが勃発します。
主人「ワンタン麺じゃないって!ただのワンタンっ?なんではっきり言わなかった!?」
奥さん「私はちゃんとワンタン一丁って言ったっぺ!あんたがちゃんと聞いてなかった!」
主人「ワンタンなんて滅多に出ねんだから、ちゃんと麺なしのワンタンって言えば良い・・・」
奥さん「そんな事言ったって・・・」
主人「全く気遣いという物がない嫌な女だ・・・」
奥さん「・・・・・」でにらみつける・・・・
この時もずいぶん気まずい思いをしましたねぇ。
それ以来、賢パパはワンタンを注文する時は必ず・・・これじゃありませんから

と断りを入れるようにしています。
昨夜色々とやってみましたが・・・ダメ。
で、先ほど会社から帰って来て・・・テクニカルセンターの方に教えていただいて・・・めでたく接続が完了です。
あ、電子メールのほうはまだ接続出来ていませんので・・・メールを読むことは出来ません。
ニューPCからの記念すべき第一弾です。
さて、もうずいぶん昔の事なのではっきりしたことは憶えていないのですが・・・
30年以上も前に仕事で神戸に行った時に・・・こんな事がありました。
神戸と言えば勿論「神戸牛」ですから・・・同じ地区に出張していた友達と一緒に・・・・鉄板焼きかなんかで神戸牛を堪能した後・・・友達と別れて宿泊先のホテルに帰ろうとしたんですが・・・
肉ってやつはすぐにお腹が一杯になるんですが・・・減るのも速いんです。
で、歩いていると・・・タイミング良くうどん屋さんの看板が目に入ります。
中に入ってビールを一本注文して・・・運ばれて来る間に食べるものをメニューから選びます。
ビールを運んで来てくれたのは歳の行ったこの店のおかみさんでしょうかねぇ。
賢パパが注文したのは「卵とじうどん」なんですが・・・「ネギを入れないで・・・」って注文をつけたんです。
おかみさんは厨房へ行って調理をしているご主人にその旨を伝えます。
するとご主人が何やら文句を言っています。
初めは気にも留めずにビールを飲んでいたのですが・・・言い争う声が次第に大きくなるので・・・嫌でも耳に入って来てしまいます。
どうやら賢パパが注文した卵とじうどんが言い争いの原因のようです。
主人「卵でネギをとじるから卵とじやないかっ!」
おかみさん「そんなこと言うたかて、入れんでええゆうとるんやから・・・」
主人「それじゃ卵とじやないわ!」
おかみさん「お客さんがそれでええゆうとるんやから・・・」
たまりかねた賢パパはご主人に謝って・・・・出来て来たのは

半泣き状態で食べましたわ。
それ以来、賢パパは卵とじうどんというものを食べたことがありません。
その20年後ぐらいに、今度はいわき市に出張した時の話ですが・・・
昼飯をラーメン屋さんで食べたのですが、当然ビールと餃子を頂きますから・・・・麺類は軽くてもOKです。
賢パパ、ラーメンはふるさとの白河ラーメンしか食べませんから・・・こういう時は大抵「ワンタン」を注文します。
で、この時もワンタンを頼んだのですが・・・出来上がろうかという頃合いになって・・・厨房の中で言い争いが勃発します。
主人「ワンタン麺じゃないって!ただのワンタンっ?なんではっきり言わなかった!?」
奥さん「私はちゃんとワンタン一丁って言ったっぺ!あんたがちゃんと聞いてなかった!」
主人「ワンタンなんて滅多に出ねんだから、ちゃんと麺なしのワンタンって言えば良い・・・」
奥さん「そんな事言ったって・・・」
主人「全く気遣いという物がない嫌な女だ・・・」
奥さん「・・・・・」でにらみつける・・・・
この時もずいぶん気まずい思いをしましたねぇ。
それ以来、賢パパはワンタンを注文する時は必ず・・・これじゃありませんから

と断りを入れるようにしています。
2011年07月01日
ササユリ
先日のハイキングの時に登山道を歩いているとこんな花が目に入りました。

ササユリという花なんですが、賢パパは静岡に来るまでこの花のことを知りませんでした。
それはなぜかと言うと・・・この花って分布が限られているからなんですね。
ものの本によれば・・・・「ササユリは本州中部地方以西~四国・九州に分布し・・・」とありますが、賢パパが指導を受けたことのある植物学の大先生は富士川から西に分布しているというのが通説だとおっしゃっていましたねぇ。
ただ、伊豆地方には「伊豆ゆり」という独特の種類があり、これはやまゆりとササユリの自然交雑種ではないかとの見方が有力だとの事でした。
もう20年も前のことになりますが、その植物学者の先生に連れられて伊豆半島の自生地まで伊豆ユリを見学に行ったことがありましたが、今ではネットで検索しても「伊豆ユリ」に関する記述は見ることが出来ません。
一体どうなってしまったんでしょうかねぇ?
おっと、本題に戻ります。
ササユリですが・・・学名をLilium japonicumと言います。
つまり「日本のユリ」というわけです。
これには「ヤマユリだって日本古来のユリなのに・・・」と異論を唱える方がおられるかも知れませんが・・・
命名者と目されているオランダ人がヤマユリのある東の地方に行ったことがなかったか、あるいは行った時期がユリの季節ではなかったのでヤマユリの標本を手に入れることが出来なかったためにこのササユリを「japonicum」と名づけたらしいというのが定説です。
賢パパは数ある花の中でもこのササユリが一番好きなのですが、その魅力は美しい姿と気高い香りに尽きます。
ヤマユリが頑丈な茎にたくさんの花をつけるのに対してこちらはか細い茎に一輪の花。
たまには二輪、三輪というのも見かけますが普通は大体一輪です。
香りもヤマユリの強烈な自己主張に比べてずっと控えめな・・・かと言って十分な存在感のある上品な香りです。
そして特筆すべきは・・・その栽培の難しさ。
かの植物学者の先生は乱獲と自然破壊によるササユリの激減に心を痛め、人工栽培で増殖が出来ればそれを自然に還すと同時に天燃香料の採取のような事業化にもつながると考え、賢パパの会社にその研究を薦めてくれたのです。
それを受け入れる形で賢パパ達が研究を始めました。
まずはササユリの自生地探しから研究に着手しましたねぇ。
そして、種子が稔る秋になると目星をつけておいた自生地に出向いて種子を採取して来ます。
これを業者さんに頼んで作ってもらった特製の箱に栽培に適した土を入れた播種箱に播くわけですが何しろ種子の数が多いので箱もハンパない数になりました。
そしてこの箱をウイルスから守るために媒介する昆虫が入ることの出来ない網室の中で管理して・・・翌年の春に芽が出ます。
1年目の苗は米粒ほどの小さな球根とたった1枚の小さな葉っぱだけで、これを気長に育てる事で3年目か4年目ぐらいでやっと茎が立つんです。
でも・・・・花が咲くのは更に1年か2年あるいは3年も後の事で種子を蒔いてから実に5,6年あるいは7年後ぐらいになってやっと初めての花が咲くのです。
この成長期間の長さを当時流行の「植物バイオテクノロジー」の技術を駆使して何とか半分ぐらいに縮められないかと様々な手段を尽くしたのでした。
結果は・・・途中撤退・・・でした。
このササユリには植物バイオもなすすべなく敗れ去りました。
この後数年で横浜に転勤となった賢パパはそれ以来このササユリにお目にかかるチャンスがほとんどありませんでした。
それが先日のハイキングで・・・・忘れかけていたこの美しいお姿に久しぶりでのご対面となり・・・・
その時の感激はとても文字で表すことは出来ません。
これだけでも大満足の賢パパだったのに・・・・8時間も歩いてバテバテになっている所に再びのサプライズでしたから・・・

疲れなんてどこかに吹っ飛んでしまい、揚々と歩いて行くと・・・

いや、もうあっちにもこっちにも・・・

疲れた身体と心に対する最高のご褒美でした。
こんな身近にあったササユリのこと・・・しっかり憶えていて・・・来年からも会いに行かなくては・・・
ササユリという花なんですが、賢パパは静岡に来るまでこの花のことを知りませんでした。
それはなぜかと言うと・・・この花って分布が限られているからなんですね。
ものの本によれば・・・・「ササユリは本州中部地方以西~四国・九州に分布し・・・」とありますが、賢パパが指導を受けたことのある植物学の大先生は富士川から西に分布しているというのが通説だとおっしゃっていましたねぇ。
ただ、伊豆地方には「伊豆ゆり」という独特の種類があり、これはやまゆりとササユリの自然交雑種ではないかとの見方が有力だとの事でした。
もう20年も前のことになりますが、その植物学者の先生に連れられて伊豆半島の自生地まで伊豆ユリを見学に行ったことがありましたが、今ではネットで検索しても「伊豆ユリ」に関する記述は見ることが出来ません。
一体どうなってしまったんでしょうかねぇ?
おっと、本題に戻ります。
ササユリですが・・・学名をLilium japonicumと言います。
つまり「日本のユリ」というわけです。
これには「ヤマユリだって日本古来のユリなのに・・・」と異論を唱える方がおられるかも知れませんが・・・
命名者と目されているオランダ人がヤマユリのある東の地方に行ったことがなかったか、あるいは行った時期がユリの季節ではなかったのでヤマユリの標本を手に入れることが出来なかったためにこのササユリを「japonicum」と名づけたらしいというのが定説です。
賢パパは数ある花の中でもこのササユリが一番好きなのですが、その魅力は美しい姿と気高い香りに尽きます。
ヤマユリが頑丈な茎にたくさんの花をつけるのに対してこちらはか細い茎に一輪の花。
たまには二輪、三輪というのも見かけますが普通は大体一輪です。
香りもヤマユリの強烈な自己主張に比べてずっと控えめな・・・かと言って十分な存在感のある上品な香りです。
そして特筆すべきは・・・その栽培の難しさ。
かの植物学者の先生は乱獲と自然破壊によるササユリの激減に心を痛め、人工栽培で増殖が出来ればそれを自然に還すと同時に天燃香料の採取のような事業化にもつながると考え、賢パパの会社にその研究を薦めてくれたのです。
それを受け入れる形で賢パパ達が研究を始めました。
まずはササユリの自生地探しから研究に着手しましたねぇ。
そして、種子が稔る秋になると目星をつけておいた自生地に出向いて種子を採取して来ます。
これを業者さんに頼んで作ってもらった特製の箱に栽培に適した土を入れた播種箱に播くわけですが何しろ種子の数が多いので箱もハンパない数になりました。
そしてこの箱をウイルスから守るために媒介する昆虫が入ることの出来ない網室の中で管理して・・・翌年の春に芽が出ます。
1年目の苗は米粒ほどの小さな球根とたった1枚の小さな葉っぱだけで、これを気長に育てる事で3年目か4年目ぐらいでやっと茎が立つんです。
でも・・・・花が咲くのは更に1年か2年あるいは3年も後の事で種子を蒔いてから実に5,6年あるいは7年後ぐらいになってやっと初めての花が咲くのです。
この成長期間の長さを当時流行の「植物バイオテクノロジー」の技術を駆使して何とか半分ぐらいに縮められないかと様々な手段を尽くしたのでした。
結果は・・・途中撤退・・・でした。
このササユリには植物バイオもなすすべなく敗れ去りました。
この後数年で横浜に転勤となった賢パパはそれ以来このササユリにお目にかかるチャンスがほとんどありませんでした。
それが先日のハイキングで・・・・忘れかけていたこの美しいお姿に久しぶりでのご対面となり・・・・
その時の感激はとても文字で表すことは出来ません。
これだけでも大満足の賢パパだったのに・・・・8時間も歩いてバテバテになっている所に再びのサプライズでしたから・・・
疲れなんてどこかに吹っ飛んでしまい、揚々と歩いて行くと・・・
いや、もうあっちにもこっちにも・・・
疲れた身体と心に対する最高のご褒美でした。
こんな身近にあったササユリのこと・・・しっかり憶えていて・・・来年からも会いに行かなくては・・・
2011年06月25日
梅雨明けいつ頃
なんだか梅雨の期間中だということを忘れてしまいそうな連日の好天ですねぇ。
当地の気温が35.3℃の猛暑日を記録した22日以来、翌日が33℃ぐらいで昨日も真夏日。
そして・・・埼玉、群馬あたりでは・・・あとちょっとで40℃という猛暑だったとか・・・
そこに持って来て連日の青空ですから本当に「梅雨、明けちゃったんぢゃないの!」なんて思っちゃいますよねぇ。
しかし、現実は・・・まだ6月ですから梅雨明けなんてするわけないですよね。
いや、6月だから梅雨明けしないって事はないのでは・・・なんて心の中で問答がありまして・・・・
それなら調べてみるのが一番と・・・・ネットで調べてみましたよ。
まず今年の梅雨の現状ですが・・・気象庁の発表は県別ではなく地域別になっているんですねぇ。
で、ご存知のように沖縄の梅雨入りが4月30日で6月9日に観測史上最も早く明けています。
我が東海地方はどうかと言いますと・・・・
5月27日に梅雨入りしましたが、これは過去60年で2番目に早い梅雨入りとなりました。
問題の梅雨明けなんですが・・・何と6月22日というのがありました。

さすがに過去60年でたったの一回だけですが1963年の6月22日に梅雨が明けていました。
もっとも、これを見るとその年は何と5月4日に梅雨入りしていますから梅雨の期間としては短くないんですねぇ。
遅い梅雨明けでは60年間で2回だけ8月に入ってからというのがありますが極めつけは1993年です。

この年は何と・・・梅雨明けの時期が不明なんですよねぇ。
天下の気象庁が「いつの間にか明けていました」って・・・・笑えますよねぇ。
なんだかこの前年とかその前の年だかに「梅雨明け宣言」した後に再び梅雨前線が下がって来て梅雨に逆戻りしてしまったことがあって気象庁が慎重になりすぎて梅雨明け宣言を出すタイミングを逃してしまった感じですよねぇ。
そんな話題はさておいて・・・これが直近10年間の梅雨入り、梅雨明けの日と梅雨の期間の長さなんですが・・・

このデータを参考にして今年の梅雨明け時期を予想するなら・・・7月の10日前後ということになりますかねぇ。
おぉ、その日は・・・海抜0mからの富士登山を予定している日ぢゃまいか!
いよいよその日が近づいて来ました。
今日はお昼ぐらいまではもちそうな予報なので・・・これからトレーニングで一歩きしてくることにしますわ。
当地の気温が35.3℃の猛暑日を記録した22日以来、翌日が33℃ぐらいで昨日も真夏日。
そして・・・埼玉、群馬あたりでは・・・あとちょっとで40℃という猛暑だったとか・・・
そこに持って来て連日の青空ですから本当に「梅雨、明けちゃったんぢゃないの!」なんて思っちゃいますよねぇ。
しかし、現実は・・・まだ6月ですから梅雨明けなんてするわけないですよね。
いや、6月だから梅雨明けしないって事はないのでは・・・なんて心の中で問答がありまして・・・・
それなら調べてみるのが一番と・・・・ネットで調べてみましたよ。
まず今年の梅雨の現状ですが・・・気象庁の発表は県別ではなく地域別になっているんですねぇ。
で、ご存知のように沖縄の梅雨入りが4月30日で6月9日に観測史上最も早く明けています。
我が東海地方はどうかと言いますと・・・・
5月27日に梅雨入りしましたが、これは過去60年で2番目に早い梅雨入りとなりました。
問題の梅雨明けなんですが・・・何と6月22日というのがありました。
さすがに過去60年でたったの一回だけですが1963年の6月22日に梅雨が明けていました。
もっとも、これを見るとその年は何と5月4日に梅雨入りしていますから梅雨の期間としては短くないんですねぇ。
遅い梅雨明けでは60年間で2回だけ8月に入ってからというのがありますが極めつけは1993年です。
この年は何と・・・梅雨明けの時期が不明なんですよねぇ。
天下の気象庁が「いつの間にか明けていました」って・・・・笑えますよねぇ。
なんだかこの前年とかその前の年だかに「梅雨明け宣言」した後に再び梅雨前線が下がって来て梅雨に逆戻りしてしまったことがあって気象庁が慎重になりすぎて梅雨明け宣言を出すタイミングを逃してしまった感じですよねぇ。
そんな話題はさておいて・・・これが直近10年間の梅雨入り、梅雨明けの日と梅雨の期間の長さなんですが・・・
このデータを参考にして今年の梅雨明け時期を予想するなら・・・7月の10日前後ということになりますかねぇ。
おぉ、その日は・・・海抜0mからの富士登山を予定している日ぢゃまいか!
いよいよその日が近づいて来ました。
今日はお昼ぐらいまではもちそうな予報なので・・・これからトレーニングで一歩きしてくることにしますわ。
2011年06月07日
ハイブリッドカー 低燃費の理由
先日久しぶりで高速道路を走りましたが、一般道と異なり対向車を見る事がありませんから前や横を走っている車をじっくり観察する事が出来ます。
で、気がついた事がありまして・・・こんな車がやたら目につくんですよねぇ。


今ではすっかりおなじみとなったハイブリッドカーですよね。
この間新型Pリウスの燃費が38Km/Lなんて記事を何かで読んだ事を思い出したんですが・・・・ハイブリッドカーって確か電気で動くんですよねぇ。
ガソリンエンジンで電気を作り出してその電気でモーターを回して走るわけですから・・・・
エンジンの他にモーターとかも積んでるわけで車体の重量はガソリン車よりも重くなってしまいますよねぇ。
しかもエネルギーを変換する時には当然ロスが生じますから・・・それだけでもガソリン車より燃費が悪いはずなのに。
運転しながら「あぁでもない、こうでもない・・」と色々考えてみましたが・・・・賢パパの乏しい知識ではお手上げでした。
そこでちょっと調べてみたんです。
すると・・・・こんな原理があったんですねぇ。
以下は全て受け売りです。
Iンサイトは30.0km/ℓ、新型Pリウスでは38.0km/ℓ(ともに10・15モード走行燃費)。
驚異的な低燃費を実現した理由は何なのでしょうか。
ハイブリッド車とは、2つ以上の異なる動力源・エネルギー源を持つ自動車のこと。
そのため、不利になる点があります。
まず、ガソリンエンジンの他にモーターと電池を積んでいること。
車が重くなるので、その分、燃費が悪化します。
それにハイブリッド車は、エンジンで発電→電力を直流に変換して充電→周波数や電圧を変換してモーターを駆動するので、 直接エンジンで駆動するだけの従来車よりエネルギーを変換して使う部分はロスが多くなります。
●『低燃費』の秘密
重くて、エネルギー変換ロスがあるというマイナス面があるのに、ハイブリッド車の燃費がいいのは、 エンジンを燃費効率のいい使用条件だけで使用するからです。
ガソリンエンジンで特に燃費効率が悪いのは、低回転から回転数を上げながら発進・加速するとき。 一方、電気モーターは、ゼロ回転からの発進時に最大の力を出すことができます。
この特性をうまく組み合わせて低燃費を実現させたのがハイブリッド車です。 減速時・ブレーキ時・下り坂などでは、捨てていたエネルギーを充電にまわすので、その点もムダがありません。
で、TヨタとHンダのハイブリッドカーでは少々方式が異なるんだそうですが原理は同じなので、動いたり止まったりを繰り返す事が多い街中走行で特に威力が発揮されるのだそうです。
それからTヨタもHンダも車体の形が似てるなぁって思いませんか?
あれは高速走行時の空気抵抗を減らして少しでも燃費を良くするためにあんなスタイルに設計されているのだそうですよ。
何げに見ていたハイブリッドカーですが色々考えて作られていたんですねぇ。
で、気がついた事がありまして・・・こんな車がやたら目につくんですよねぇ。


今ではすっかりおなじみとなったハイブリッドカーですよね。
この間新型Pリウスの燃費が38Km/Lなんて記事を何かで読んだ事を思い出したんですが・・・・ハイブリッドカーって確か電気で動くんですよねぇ。
ガソリンエンジンで電気を作り出してその電気でモーターを回して走るわけですから・・・・
エンジンの他にモーターとかも積んでるわけで車体の重量はガソリン車よりも重くなってしまいますよねぇ。
しかもエネルギーを変換する時には当然ロスが生じますから・・・それだけでもガソリン車より燃費が悪いはずなのに。
運転しながら「あぁでもない、こうでもない・・」と色々考えてみましたが・・・・賢パパの乏しい知識ではお手上げでした。
そこでちょっと調べてみたんです。
すると・・・・こんな原理があったんですねぇ。
以下は全て受け売りです。
Iンサイトは30.0km/ℓ、新型Pリウスでは38.0km/ℓ(ともに10・15モード走行燃費)。
驚異的な低燃費を実現した理由は何なのでしょうか。
ハイブリッド車とは、2つ以上の異なる動力源・エネルギー源を持つ自動車のこと。
そのため、不利になる点があります。
まず、ガソリンエンジンの他にモーターと電池を積んでいること。
車が重くなるので、その分、燃費が悪化します。
それにハイブリッド車は、エンジンで発電→電力を直流に変換して充電→周波数や電圧を変換してモーターを駆動するので、 直接エンジンで駆動するだけの従来車よりエネルギーを変換して使う部分はロスが多くなります。
●『低燃費』の秘密
重くて、エネルギー変換ロスがあるというマイナス面があるのに、ハイブリッド車の燃費がいいのは、 エンジンを燃費効率のいい使用条件だけで使用するからです。
ガソリンエンジンで特に燃費効率が悪いのは、低回転から回転数を上げながら発進・加速するとき。 一方、電気モーターは、ゼロ回転からの発進時に最大の力を出すことができます。
この特性をうまく組み合わせて低燃費を実現させたのがハイブリッド車です。 減速時・ブレーキ時・下り坂などでは、捨てていたエネルギーを充電にまわすので、その点もムダがありません。
で、TヨタとHンダのハイブリッドカーでは少々方式が異なるんだそうですが原理は同じなので、動いたり止まったりを繰り返す事が多い街中走行で特に威力が発揮されるのだそうです。
それからTヨタもHンダも車体の形が似てるなぁって思いませんか?
あれは高速走行時の空気抵抗を減らして少しでも燃費を良くするためにあんなスタイルに設計されているのだそうですよ。
何げに見ていたハイブリッドカーですが色々考えて作られていたんですねぇ。
2011年06月04日
3倍体
昨夜はちょっと得した気分になりましたよ。
今日これから娘の引っ越しで首都圏まで行かなくてはいけないので・・・飲み会を早引けして帰ろうと店の外に出た時にタイミング良くバスが来たんです。
一瞬、乗ろうかなとも思ったんですが乗らずに歩いて帰って来ると・・・途中の小川の所でホタルを観る事が出来ましたよ。
それも一箇所だけではなく、もう一箇所でも・・・・いやぁ~こんな近くでも観る事が出来るんですねぇ。
さて、今日の話題です。
ちょっと耳慣れない言葉かも知れませんがご存知の方もおられると思います。
わかりやすく解説してみましょう。
中学生の理科の時間に教わった事を思い出してください。
普通の生き物は、父と母から一組ずつもらった、二組の染色体を持っていますよねぇ。
この染色体の一組をnで表して、普通の生き物は二組ですから2nの染色体を持つ事になりnの2倍なので2倍体と呼んでいるのでしたね。
自然界では2倍体しか存在しないのですが・・・魚の受精卵をぬるま湯につけると、その卵からは2組ではなく3組の染色体を持った子供が産まれる事が知られています。
3組の染色体ですから3nと言う事で3倍体と呼ばれるわけなのです。
そしてこの 3倍体になると、成長はするけれど成熟したオスやメスにはならないという性質があります。
つまりメスの3倍体魚は、卵を産まない体になるというわけです。
普通の場合はメスの魚は成熟すると卵をつくる方に栄養を取られてしまい、成長が止まってしまい肉質も落ちます。
それに、産卵が終わると死んでしまいます。
ところが3倍体のメスは卵を産まないので栄養を取られることなく成長し続け、おいしい肉質のまま大きな魚になるんだそうです。
どのくらい大きくなるのかと言いますと・・・・

2倍体のアマゴと3倍体のアマゴですがこんなに大きくなるのだそうですからびっくりです。
他にも3倍体の性質を利用したものが我々の身近にもありますよ。
3倍体は動物の場合は卵を作りませんが、植物でも同じなんです。
我々がしばしば口にする種なしブドウや種なしスイカ。
そうなんです、あれも3倍体の性質を利用した産物なんですよねぇ。
他にもないかと思って色々調べてみたらこんなびっくりするようなニュースがありました。
http://www.f7.dion.ne.jp/~moorend/news/2008021201.html
でも・・・新聞の名前が名前ですから・・・信用は出来ませんがね。
今日これから娘の引っ越しで首都圏まで行かなくてはいけないので・・・飲み会を早引けして帰ろうと店の外に出た時にタイミング良くバスが来たんです。
一瞬、乗ろうかなとも思ったんですが乗らずに歩いて帰って来ると・・・途中の小川の所でホタルを観る事が出来ましたよ。
それも一箇所だけではなく、もう一箇所でも・・・・いやぁ~こんな近くでも観る事が出来るんですねぇ。
さて、今日の話題です。
ちょっと耳慣れない言葉かも知れませんがご存知の方もおられると思います。
わかりやすく解説してみましょう。
中学生の理科の時間に教わった事を思い出してください。
普通の生き物は、父と母から一組ずつもらった、二組の染色体を持っていますよねぇ。
この染色体の一組をnで表して、普通の生き物は二組ですから2nの染色体を持つ事になりnの2倍なので2倍体と呼んでいるのでしたね。
自然界では2倍体しか存在しないのですが・・・魚の受精卵をぬるま湯につけると、その卵からは2組ではなく3組の染色体を持った子供が産まれる事が知られています。
3組の染色体ですから3nと言う事で3倍体と呼ばれるわけなのです。
そしてこの 3倍体になると、成長はするけれど成熟したオスやメスにはならないという性質があります。
つまりメスの3倍体魚は、卵を産まない体になるというわけです。
普通の場合はメスの魚は成熟すると卵をつくる方に栄養を取られてしまい、成長が止まってしまい肉質も落ちます。
それに、産卵が終わると死んでしまいます。
ところが3倍体のメスは卵を産まないので栄養を取られることなく成長し続け、おいしい肉質のまま大きな魚になるんだそうです。
どのくらい大きくなるのかと言いますと・・・・

2倍体のアマゴと3倍体のアマゴですがこんなに大きくなるのだそうですからびっくりです。
他にも3倍体の性質を利用したものが我々の身近にもありますよ。
3倍体は動物の場合は卵を作りませんが、植物でも同じなんです。
我々がしばしば口にする種なしブドウや種なしスイカ。
そうなんです、あれも3倍体の性質を利用した産物なんですよねぇ。
他にもないかと思って色々調べてみたらこんなびっくりするようなニュースがありました。
http://www.f7.dion.ne.jp/~moorend/news/2008021201.html
でも・・・新聞の名前が名前ですから・・・信用は出来ませんがね。
2011年05月28日
橙・・・へぇ~!
昨日は会社に行くのに家を出る時、「今日は木曜日だなぁ」と思って出掛けたので・・・1日得した気分です。
さて、先日の賢の散歩の時、こんなものに気づきました。

同じ夏みかんの木ですよ。
こんな花と

実が一緒に着いてるんです。
普通の植物って・・・花が咲いて受粉して・・・実がなるはずなのに・・・
一体どうして・・・と疑問を持ったらすぐに調べるのが賢パパの良い所です。
色々調べてみましたが・・・・どうやら夏みかんなどのミカン科の植物は実の「もち」が良いのだそうです。
だから、取らないでおけばなかなか落果しないで残っているのだとか・・・
それで、放置しておくと次の花が咲いてしまうという事なんですねぇ。
これで疑問は解消ですが・・・調べているうちに面白い記事を見つけました。
それは同じミカン科の植物である橙についてのものです。

正月のお供え餅の上に橙を載せるのは「代々(だいだい)栄えるように・・・」のかけことばというのは知っていましたが・・・・
問題はその橙の名前の由来なんです。
なんと、この橙なんですが・・・実のもちが良くて・・・放っておくと何年も実が落ちないで着いたままでいて・・・翌年の実がなっても更に次の年の実がなっても代々の実が着いているのだそうです。
それで・・・・代々が転じて橙になったんだそうで・・・・まさに目からウロコ・・・ですよねぇ。
落ちがなくてすみませんが、実もちの良い実だけに・・・「落ち ない」んです。
さて、先日の賢の散歩の時、こんなものに気づきました。
同じ夏みかんの木ですよ。
こんな花と
実が一緒に着いてるんです。
普通の植物って・・・花が咲いて受粉して・・・実がなるはずなのに・・・
一体どうして・・・と疑問を持ったらすぐに調べるのが賢パパの良い所です。
色々調べてみましたが・・・・どうやら夏みかんなどのミカン科の植物は実の「もち」が良いのだそうです。
だから、取らないでおけばなかなか落果しないで残っているのだとか・・・
それで、放置しておくと次の花が咲いてしまうという事なんですねぇ。
これで疑問は解消ですが・・・調べているうちに面白い記事を見つけました。
それは同じミカン科の植物である橙についてのものです。

正月のお供え餅の上に橙を載せるのは「代々(だいだい)栄えるように・・・」のかけことばというのは知っていましたが・・・・
問題はその橙の名前の由来なんです。
なんと、この橙なんですが・・・実のもちが良くて・・・放っておくと何年も実が落ちないで着いたままでいて・・・翌年の実がなっても更に次の年の実がなっても代々の実が着いているのだそうです。
それで・・・・代々が転じて橙になったんだそうで・・・・まさに目からウロコ・・・ですよねぇ。
落ちがなくてすみませんが、実もちの良い実だけに・・・「落ち ない」んです。
2011年05月14日
つつじとさつき
桜の季節が終わってしばらくすると目に付くようになるのがこんな花ですねぇ。
街の中でも

山を歩いていても

色々な種類があります。
で、もうすぐ咲き出すのがこの花です。

つつじとさつきなんですが・・・区別がつきにくいですよねぇ。
区別のつきにくい花としては「コブシとモクレン」や「アヤメ、カキツバタと花菖蒲」なんてのがありましたがこれらは何とか区別法がわかりました。
そこで賢パパ、ついでと言っては何ですが・・・さつきとつつじの見分け方を調べてみましたよ。
まず、植物学的な分類ではどちらも「ツツジ科ツツジ属」なんですよねぇ。
で、さつきの正式名称が「さつきつつじ」だそうですから「さつき」はつつじの1種なんですね。

肝心の見分け方なんですが、一番簡単なのは花が咲く時期らしいですよ。
さつきはその名の通り旧暦の皐月、つまり5月ですので今の暦の5月から6月ぐらいに咲くのだそうですから4月に咲き始めるツツジの方がずいぶん早く咲くんです。
つつじはもう終わりかけていますが

さつきはまだこんなつぼみです。

後は、葉の大きさなども比べてみるとだいぶ違いますねぇ。
これがつつじで

これがさつき

こうして比べると・・・大きさだけでなくつつじは軟らかでツヤがなく、さつきは硬くてツヤツヤしています。
まぁ、こんな見分け方で区別する事が出来るのだそうですが・・・このつつじの木ってクモやダニの巣になっているんですよねぇ。
うちの賢の野郎はすぐにツツジの木の中に首を突っ込むのでこれからの季節はダニが付いて大変なんです。

あっ、それから・・・つつじともさつきとも全然関係のない話題なんですが、今朝の散歩の時にGSの横を通りましてね・・・

知らない間にずいぶん値上がりしてたんですねぇ。
そんなわけで今日も又お金のかからない・・・・ウォーキングに行って来ますわ。
街の中でも
山を歩いていても
色々な種類があります。
で、もうすぐ咲き出すのがこの花です。

つつじとさつきなんですが・・・区別がつきにくいですよねぇ。
区別のつきにくい花としては「コブシとモクレン」や「アヤメ、カキツバタと花菖蒲」なんてのがありましたがこれらは何とか区別法がわかりました。
そこで賢パパ、ついでと言っては何ですが・・・さつきとつつじの見分け方を調べてみましたよ。
まず、植物学的な分類ではどちらも「ツツジ科ツツジ属」なんですよねぇ。
で、さつきの正式名称が「さつきつつじ」だそうですから「さつき」はつつじの1種なんですね。
肝心の見分け方なんですが、一番簡単なのは花が咲く時期らしいですよ。
さつきはその名の通り旧暦の皐月、つまり5月ですので今の暦の5月から6月ぐらいに咲くのだそうですから4月に咲き始めるツツジの方がずいぶん早く咲くんです。
つつじはもう終わりかけていますが
さつきはまだこんなつぼみです。
後は、葉の大きさなども比べてみるとだいぶ違いますねぇ。
これがつつじで
これがさつき
こうして比べると・・・大きさだけでなくつつじは軟らかでツヤがなく、さつきは硬くてツヤツヤしています。
まぁ、こんな見分け方で区別する事が出来るのだそうですが・・・このつつじの木ってクモやダニの巣になっているんですよねぇ。
うちの賢の野郎はすぐにツツジの木の中に首を突っ込むのでこれからの季節はダニが付いて大変なんです。
あっ、それから・・・つつじともさつきとも全然関係のない話題なんですが、今朝の散歩の時にGSの横を通りましてね・・・
知らない間にずいぶん値上がりしてたんですねぇ。
そんなわけで今日も又お金のかからない・・・・ウォーキングに行って来ますわ。
2011年04月24日
菖蒲と花菖蒲
昨日の記事でどうやらこれは花菖蒲らしいという事が分かりました。(賢パパ的にはまだ納得はしていませんが)

花菖蒲が出たついでと言っては何ですが・・・・意外に間違って覚えられているのが花菖蒲と菖蒲の違いなんですよねぇ。
菖蒲に「花」が付いているので・・・桃と花桃、海棠と花海棠とか水木と花水木のように同じ仲間の植物だと思われている方が・・・・
ところが・・・です。
菖蒲と花菖蒲は全然違う種類の植物なんですよねぇ。
ちょっと調べてみると
ハナショウブ(花菖蒲、Iris ensata var. ensata)はアヤメ科アヤメ属の多年草である。
ショウブ: サトイモ科 の多年草。
何と菖蒲は「サトイモ科」の植物なんですよねぇ。
この違いは両者の花を比べれば納得出来ると思います。
これが菖蒲の花で

アップで見ると

あやめ科の植物とは似ても似つかない花ですよねぇ。
ちなみに「菖蒲湯」に入れるのがこちらの菖蒲です。
今日は天気良さそうだけど、昨日の降りでは山道は泥んこでしょうねぇ。
トレーニングでコンクリ道でも歩いて来る事にしましょうかね。
花菖蒲が出たついでと言っては何ですが・・・・意外に間違って覚えられているのが花菖蒲と菖蒲の違いなんですよねぇ。
菖蒲に「花」が付いているので・・・桃と花桃、海棠と花海棠とか水木と花水木のように同じ仲間の植物だと思われている方が・・・・
ところが・・・です。
菖蒲と花菖蒲は全然違う種類の植物なんですよねぇ。
ちょっと調べてみると
ハナショウブ(花菖蒲、Iris ensata var. ensata)はアヤメ科アヤメ属の多年草である。
ショウブ: サトイモ科 の多年草。
何と菖蒲は「サトイモ科」の植物なんですよねぇ。
この違いは両者の花を比べれば納得出来ると思います。
これが菖蒲の花で

アップで見ると

あやめ科の植物とは似ても似つかない花ですよねぇ。
ちなみに「菖蒲湯」に入れるのがこちらの菖蒲です。
今日は天気良さそうだけど、昨日の降りでは山道は泥んこでしょうねぇ。
トレーニングでコンクリ道でも歩いて来る事にしましょうかね。
2011年04月23日
いずれあやめかかきつばた
先週ぐらいから賢の散歩の時にこんな花を目にするようになりましたね。

毎年この花の時期になると悩ましいですよねぇ。
いくら考えてもこの花の名前がわからないからないんです。
正確にはわからないと言うよりは区別がつかないのですが・・・
そりゃねぇ、昔から「いずれあやめかかきつばた」って言葉があるぐらいですから、あやめかかきつばたかの見分けがつかないのは仕方がないんですが・・・これに花菖蒲が加わりますから大変ですよねぇ。
で、まるっきり区別がつかないのもしゃくに障るので例のあれで・・・調べてみたんです。
すると
アヤメは山野の草地に生える(特に湿地を好むことはない)。葉は直立し高さ40~60cm程度。5月ごろに径8cmほどの紫色の花を1-3個付ける。外花被片(前面に垂れ下がった花びら)には網目模様があるのが特徴で、本種の和名のもとになる。花茎は分岐しない。北海道から九州まで分布する。
カキツバタは湿地に群生し、5月から6月にかけて紫色の花を付ける。内花被片が細く直立し,外花被片(前面に垂れ下がった花びら)の中央部に白ないし淡黄色の斑紋があることなどを特徴とする。
ハナショウブはノハナショウブ(学名I. ensata var. spontanea)の園芸種である。
ではノハナショウブを見てみると
花茎の高さは40cmから100cmになり、葉は剣形で全縁。花期は6月から7月で、赤紫色の花びらの基部に黄色のすじが入るのが特徴。アヤメには網目模様が入り、カキツバタには白色から淡黄色のすじが入る。
うぅ~ん、これを読んだだけでは区別の仕方がわかりません。
それならば手っ取り早く「見分け方」で検索してみることにします。
すると・・・
ごく簡単に言いますと、花びらの基のところに、花菖蒲は黄色、カキツバタは白、アヤメは網目状の模様が、それぞれあることで区別できます。
えぇ~っ、たったこれだけですか・・・
ほんとにこれで区別出来るんでしょうかねぇと先程撮って来た写真を見てみます。

黄色のスジですから・・・花菖蒲って事になるんですかねぇ?
それならもう一枚

何だか良くわかりませんよねぇ~。
やっぱり「いずれあやめかかきつばた」って事にしておきましょうかね。

毎年この花の時期になると悩ましいですよねぇ。
いくら考えてもこの花の名前がわからないからないんです。
正確にはわからないと言うよりは区別がつかないのですが・・・
そりゃねぇ、昔から「いずれあやめかかきつばた」って言葉があるぐらいですから、あやめかかきつばたかの見分けがつかないのは仕方がないんですが・・・これに花菖蒲が加わりますから大変ですよねぇ。
で、まるっきり区別がつかないのもしゃくに障るので例のあれで・・・調べてみたんです。
すると
アヤメは山野の草地に生える(特に湿地を好むことはない)。葉は直立し高さ40~60cm程度。5月ごろに径8cmほどの紫色の花を1-3個付ける。外花被片(前面に垂れ下がった花びら)には網目模様があるのが特徴で、本種の和名のもとになる。花茎は分岐しない。北海道から九州まで分布する。
カキツバタは湿地に群生し、5月から6月にかけて紫色の花を付ける。内花被片が細く直立し,外花被片(前面に垂れ下がった花びら)の中央部に白ないし淡黄色の斑紋があることなどを特徴とする。
ハナショウブはノハナショウブ(学名I. ensata var. spontanea)の園芸種である。
ではノハナショウブを見てみると
花茎の高さは40cmから100cmになり、葉は剣形で全縁。花期は6月から7月で、赤紫色の花びらの基部に黄色のすじが入るのが特徴。アヤメには網目模様が入り、カキツバタには白色から淡黄色のすじが入る。
うぅ~ん、これを読んだだけでは区別の仕方がわかりません。
それならば手っ取り早く「見分け方」で検索してみることにします。
すると・・・
ごく簡単に言いますと、花びらの基のところに、花菖蒲は黄色、カキツバタは白、アヤメは網目状の模様が、それぞれあることで区別できます。
えぇ~っ、たったこれだけですか・・・
ほんとにこれで区別出来るんでしょうかねぇと先程撮って来た写真を見てみます。
黄色のスジですから・・・花菖蒲って事になるんですかねぇ?
それならもう一枚
何だか良くわかりませんよねぇ~。
やっぱり「いずれあやめかかきつばた」って事にしておきましょうかね。
2011年04月14日
ガルバニー電流

いきなりこんな写真で何事かと思われた方もいらっしゃいますかねぇ?
タイトルだけ見ると難しそうな印象を受けるかも知れませんが、今日の話題は皆さんの身近にあるものなんです。
先日の昼食にこんなものをいただいた賢パパですが・・・
融けたチーズにくっついてしまったアルミホイルを誤ってトーストと一緒に口の中に入れてしまったんです。
すると・・・口の中に広がるあの何とも言えない嫌ぁ~な感覚です。
虫歯のない方にはわからないかと思いますが、虫歯を抜いて差し歯を入れている方ならどなたでも一度は経験した事があるのではないでしょうか?
前々から気になってはいたのですが、ついついそのままほったらかしにしていたので・・・時間のある時にちょっと調べてみたんです。
すると「ガルバニー電流」という名前がついているんですねぇ。
歯科大辞典によりますと
「ガルバニック電流(ガルバニー電流)とは、異種金属が唾液を介して接触した時に流れる、微弱な電流のことです。
アルミ箔を噛むとキーンとなりますが、あれもガルバニック電流の一種です。」
それにしても・・・あの感覚って何度経験しても・・・嫌ぁ~な感覚ですよねぇ。